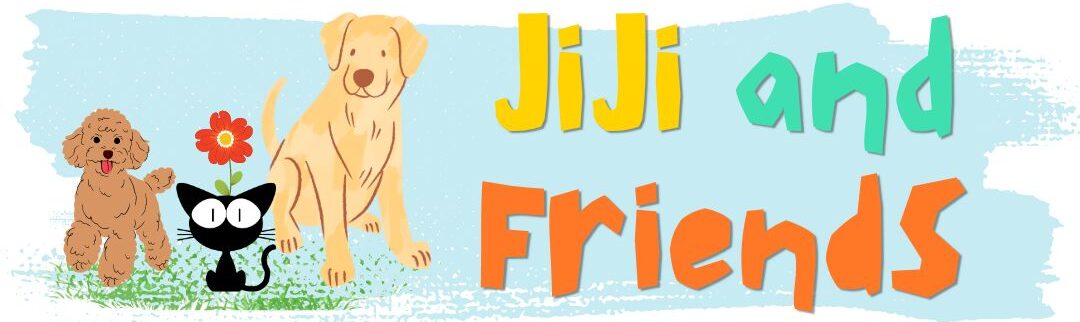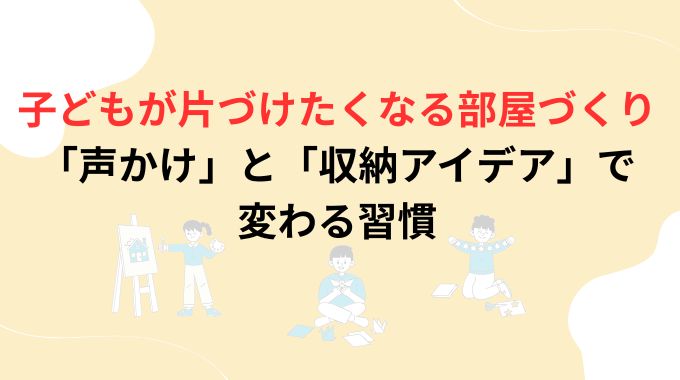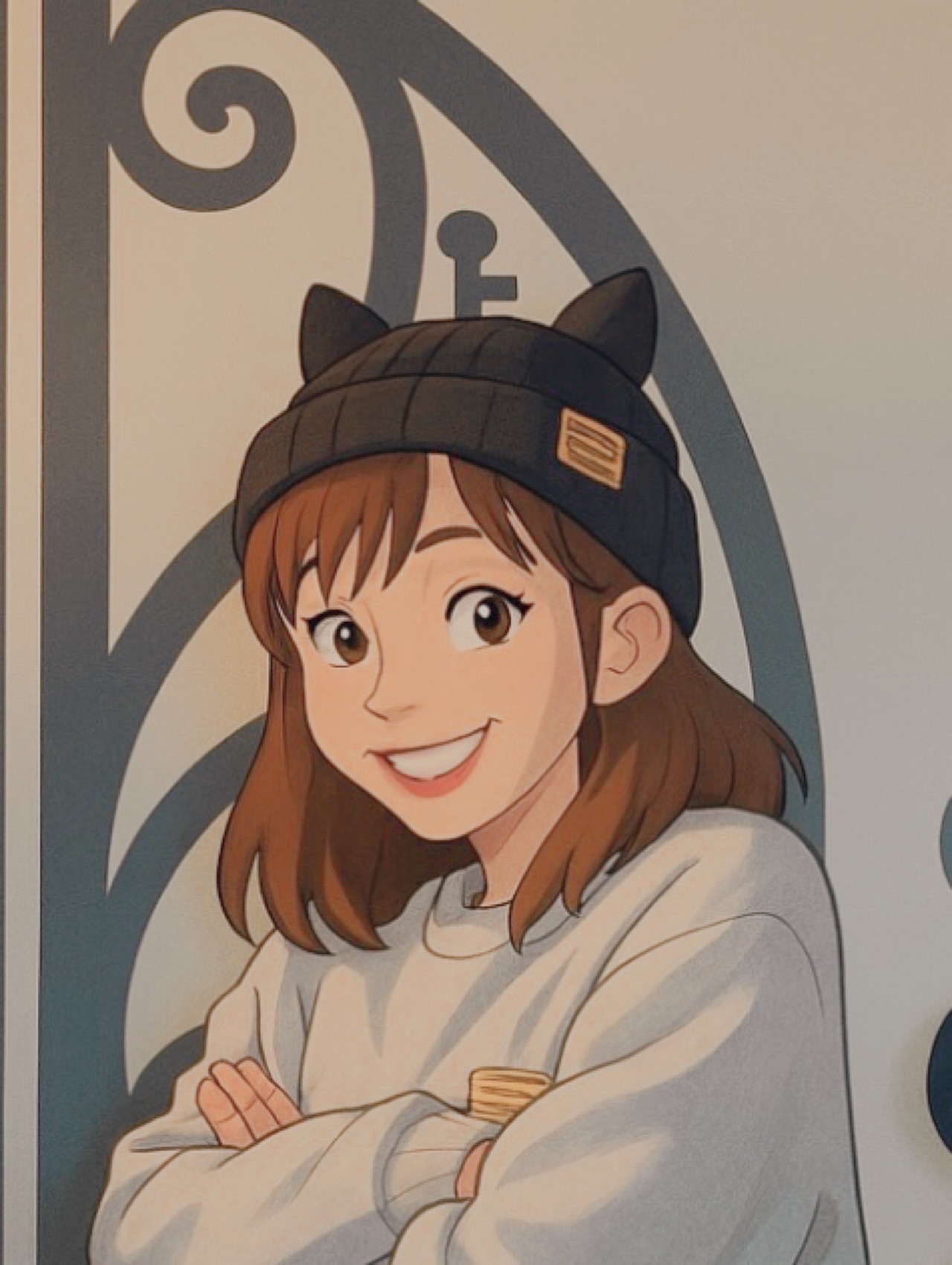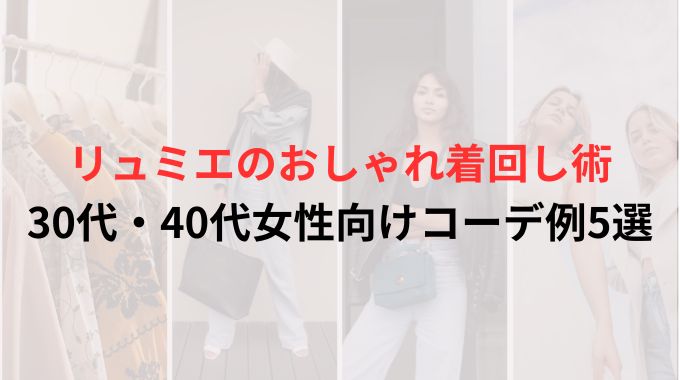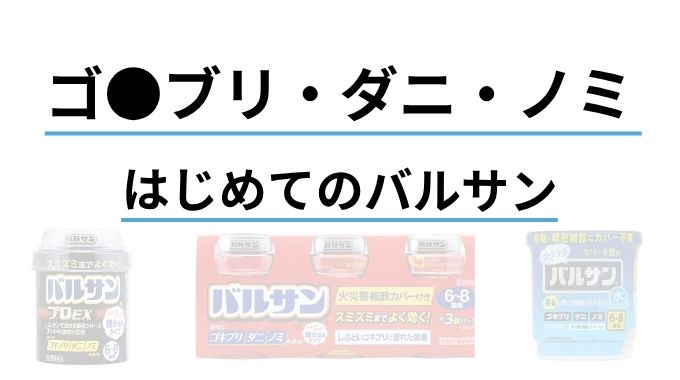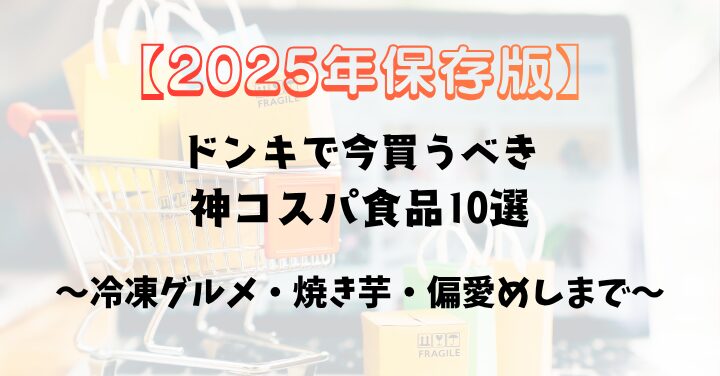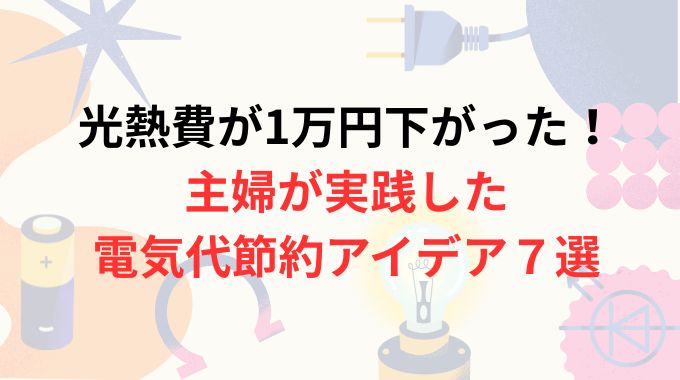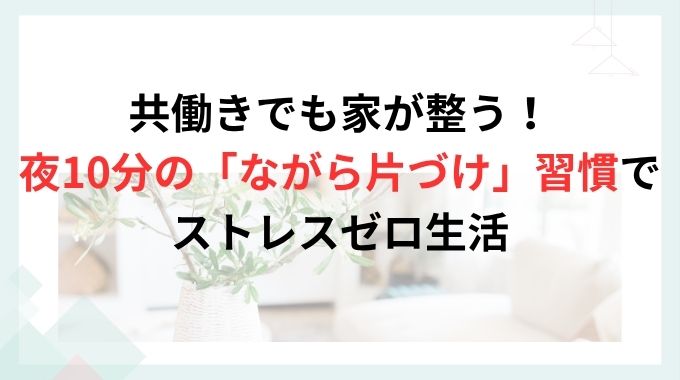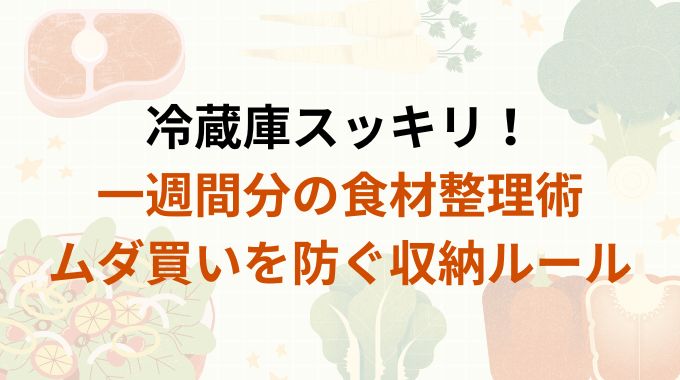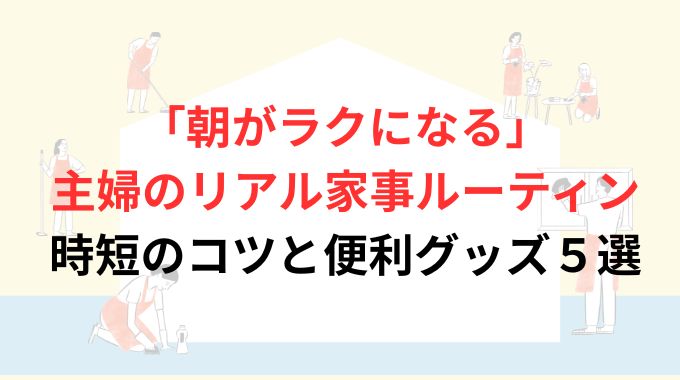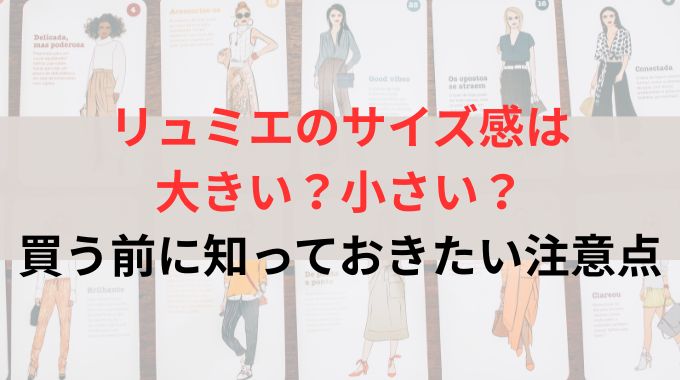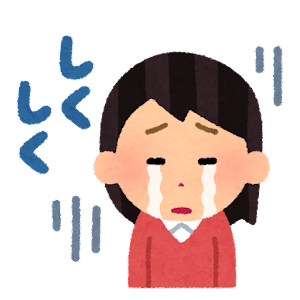 しん子
しん子毎日子どもに「片付けしなさい」って言ってる気がするけど、全然片付かない…。
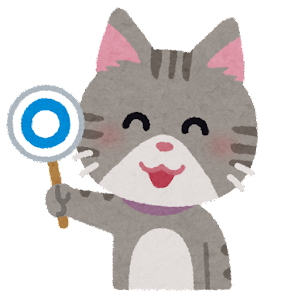
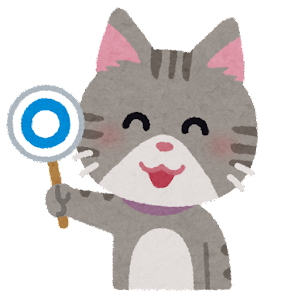
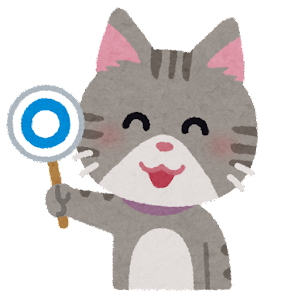
実は、子どもには言葉で促すだけじゃなくて、「片づけたくなる環境」をつくることが大事なんです!
今回の記事では、子どもが片付けたくなる部屋づくりや、声かけ、収納アイデアをどーんとご紹介します。
ママが頑張って片づけるのではなく、子どもが自分から動くようになる仕組みづくりを一緒に考えていきましょう!
是非この記事を参考に、今までの習慣を変えてみてください♪
気分もお部屋もスッキリ過ごしましょう!
「片づけなさい」を卒業!子どもが動きたくなるお部屋づくりのコツ





子どもに「片づけて〜!」とお願いしても、全然動かない…そんな悩み、あるあるですよね。
実は、「片づけない=性格の問題」ではなく、「片づけたくなる環境ができていない」だけなんです。



子どもって、目の前にあるものにすぐ夢中になりやすいですよね!
でも逆に言えば、「片づけやすい」「わかりやすい」仕組みを作ってあげるだけで、びっくりするくらい行動が変わります。
下記の表のような部屋を例に考えてみましょう!
【部屋の環境例と子どもの反応】
| 部屋のタイプ | 子どもの反応 | 改善方法 |
|---|---|---|
| フタ付きの収納ボックスが多い | 開けるのが面倒で出しっぱなし | フタなしの外からも見える透明ボックスを使う |
| 種類別に細かく分けすぎた収納 | どこに入れたらいいかわからない | 種類は大きく分ける |
| おもちゃ棚の位置が高い | 取り出せない・戻せない | 子どもの手の届く場所に置く |
このように、子ども目線の収納環境を整えるだけで、「やらされる片づけ」から「自分でできる片づけ」に変わるんです。
大切なのは、「きれいに見える部屋」ではなく、「子どもが片づけを完結できる部屋」にすること。



ママがラクになるのはもちろん、子どもも「自分でできた!」という達成感を感じられるようになります。
次では、そんな「片づけたくなる部屋づくり」のポイントを3つに分けてご紹介します♪
【子どもが片付けたくなる部屋作りポイント】
- 収納を子どもの高さ&動線に合わせる
- 分類はざっくりでOK!
- 「自分のスペース」を作る
① 子どもの高さ&動線に合わせる
子どもが片づけられない理由の一つが、「物理的にやりにくい」ということ。



棚の高さが合わなかったり、片づけ場所が遠かったりすると、それだけでやる気がなくなります。
【ポイント】
- 目線・手の届く高さに収納を設置する
→ 目線の高さより上は「取り出しやすい」けど「戻しにくい」。
よく使うおもちゃや本は“子どもがしゃがまなくても届く位置”に置くのがベスト。 - 使う場所の近くに収納を置く
→ リビングで遊ぶなら、収納もリビングの一角に。
「遊ぶ→片づける」がワンアクションで済むように動線を意識。 - 棚の数を増やしすぎない
→ “あれもこれも”収納すると、結局どこに何を入れたか混乱しがち。
お気に入りのものだけを残す整理も一緒に行うと◎。
【注意点】
- 高さを合わせすぎると、赤ちゃんの誤飲リスクがあるので注意。
- 家具を固定して、転倒防止対策も忘れずに。
- 「届かない=ママが取る」は本人の自立を妨げるので、成長に合わせて見直す。
「使う→戻す」がスムーズにできる配置こそ、片づけが「自然に身につく」第一歩です!
② 分類はざっくりでOK!
「細かく分けた方がきれいになる」と思いがちですが、実は真逆。



子どもは細かい分類を覚えるのが苦手なので、ざっくり分けた方が長続きするんです。
【ポイント】
- カテゴリーは3つまで!
→ 例:「乗り物」「ぬいぐるみ」「工作グッズ」くらいで十分。
多すぎると迷って放り込めなくなります。 - 箱やカゴの中は“見える化”
→ フタなし・透明ボックス・ラベルを絵でつけるなど、
子どもが“感覚でわかる”収納が◎。 - 増えた分だけ減らすルールを
→ 「新しいおもちゃが入るなら、ひとつお別れ」ルールを習慣化。
物の“循環”を教えることで、片づけが自然な行動に。
【注意点】
- ママが“完璧な整頓”を求めすぎないこと。
多少ごちゃっとしてても、「箱に入っていればOK」にする。 - 分類ルールは“子どもと一緒に決める”のがポイント。
自分で決めると、責任感とやる気がアップします。
ざっくり収納にすることで、片づけのハードルが下がり、「自分でできた!」がどんどん増えますよ。
③ 「自分のスペース」を作る
実はこれが一番の「やる気スイッチ」。



自分のものを置ける「マイコーナー」があるだけで、子どもは驚くほど変わります!
【ポイント】
- 1段分でもいいから「ここは○○の棚」と決める
→ 本棚や収納ラックの一角を“マイスペース”に。
「ここは自分の!」という感覚が、自主的な管理につながります。 - お気に入りを飾るコーナーをつくる
→ 宝物・絵・作品などを置ける場所を用意。
“見せる収納”を楽しむことで、自然と整える意識が芽生えます。 - 片づけが終わったら一緒に褒める
→ 「自分のスペースがきれい!」と視覚的に確認できると、
達成感が生まれ、習慣として定着しやすくなります。
【注意点】
- ほかの兄弟姉妹とスペースを分けるときは、境界をはっきりさせる。
- 飾りすぎると逆に散らかるので、定期的に“入れ替えタイム”を設けて◎。



「自分の場所をきれいにする」って、大人にとっても気持ちいいですよね。
その感覚を小さいうちから体験させてあげると、自然と整理整頓の習慣が育っていきます!
たった一言で子どもが動く!声かけ&収納アイデアで変わる習慣





「片づけなさい!」と何度言っても、子どもが全然動かない…。
これ、実は「やる気のスイッチ」を押せていないだけなんです。
片づけって、ただ物を戻す行動じゃなくて、自分で考えて動く力を育てる習慣づくり。
だからこそ、やる気を引き出す「声かけ」と「収納の工夫」がセットで大事なんです!



「どうせやらないから」「私がやった方が早い」と思ってしまう気持ち、よ〜くわかります。
でも、ほんの少し「伝え方」と「片づけ方」を変えるだけで、子どもの行動がガラッと変わることがあります。
たとえば、こんな違いがあります。
【ママの声かけと子どもの反応例】
| ママの声かけ・収納 | 子どもの反応 | 結果 |
|---|---|---|
| 「早く片づけて!」と命令口調 | 「あとで〜」とスルー | やらされ感MAXでやる気ゼロ |
| 「どっちから片づける?」と選ばせる | 主体的に動く | 自分で考える習慣がつく |
| フタ付き・奥まった収納 | 出しにくく戻しにくい | 出しっぱなしが続く |
| フタなし・見える収納 | “ここに戻す”がわかる | 片づけ完了率アップ! |



つまり、言葉と環境の「小さな見直し」が、子どもの行動スイッチになるんです。
次からは、「声かけ」と「収納アイデア」、それぞれで具体的にどんな工夫が効果的なのかをご紹介します♪
① 「声かけ」でやる気スイッチを入れる
子どもに「片づけて」と言うとき、無意識に「命令口調」になっていませんか?



実はその一言が、やる気を一気に下げていることも。
子どもは「認められる」「選べる」「一緒にやれる」と感じたときに動きやすいんです。
だから、「指示」ではなく「共感+提案」の声かけが効果的。
【ポイント】
- 選択肢を与える
→「どっちから片づけようか?」「どの箱に入れる?」
“自分で選ぶ”ことで、主体性が生まれます。 - タイミングを工夫する
→「ごはんの前に一緒に片づけよう」など、次の予定を見える形で伝えると◎。
「終わったら〇〇しようね」も効果的。 - 小さな成功をほめる
→「おもちゃさん、ちゃんとおうちに帰ったね〜!」と具体的に褒めると達成感アップ。
“行動”を認めてあげるのがポイントです。 - 一緒にスタートする
→ 最初の1分だけママも参加。
その後は「じゃあ○○くんにバトンタッチ!」で、自分で続けるきっかけに。
【注意点】
- 「なんでできないの?」など否定ワードはNG。
→ プライドが傷ついて逆効果。 - 完璧を求めすぎない。
→ 子どもの基準で「片づいた!」ならOK。 - 声のトーンにも注意。
→ 優しい口調で伝えるだけでも、反応が変わります。
声かけの目的は「片づけさせる」ではなく、「片づけようと思える気持ちを育てる」ことです♪
② 「収納アイデア」で習慣化をサポート
声かけでやる気を出しても、収納が使いづらいと続きません。
子どもにとっての「片づけやすさ」は、「迷わないこと」と「すぐ終わること」。



この2つを満たす収納を作ると、自然に習慣化します。
【ポイント】
- フタなし収納が最強!
→ 開ける手間がないだけで、片づけ率UP。
カラーボックス+布製ボックスの組み合わせもおすすめ。 - 「見える収納」で迷わない
→ 透明ボックスやラベル(絵や写真)を使って、“ここが○○の場所”を明確に。
ひらがなが読めない子にもわかりやすい! - よく使う物は手前・低い位置に
→ 頻度の高いおもちゃほど、取り出しやすく戻しやすい場所へ。
「使う→戻す」が自然にできる配置を意識。 - カテゴリーごとに色を変える
→ 「赤い箱=ぬいぐるみ」「青い箱=ブロック」など、色で覚えると整理がラクに。 - “片づけステーション”をつくる
→ リビングの一角や子ども部屋の入口などに、小さなボックスを置く。
出入りついでに“ポイッと片づけ”が習慣になります。
【注意点】
- 収納を増やしすぎない。
→「とりあえず入れとこう」になりやすく、逆に片づかなくなる。 - 見た目より「使いやすさ」を優先。
→ おしゃれ収納も、子どもにとってはハードルが高い場合あり。 - 定期的に見直す。
→ 成長に合わせて“高さ”や“使う物”が変わるため、半年に一度の棚替えを。
収納は、子どもの自立をサポートするツール。
「片づけられる仕組み」を作ってあげれば、声かけの回数もグッと減って、ママもラクになります!



この「声かけ」と「収納アイデア」の合わせ技こそ、子どもが自分で動くようになる一番の近道ですね。
マネするだけで片づく!100均アイテムで作る「子どもが戻せる収納」


「子どもが片づけたくなる部屋づくり」において、収納環境を変えるには高価な家具をそろえる必要はありません!
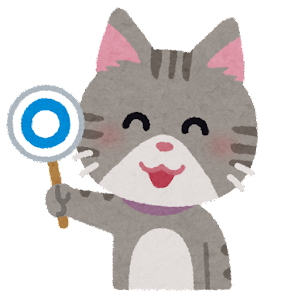
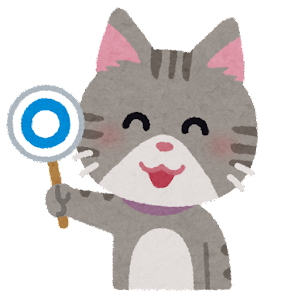
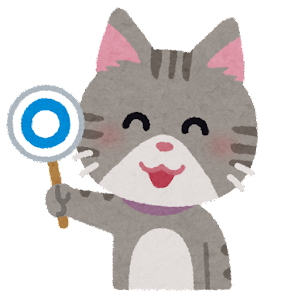
実は、手頃な価格で手に入る100均(100円ショップ)グッズでも十分に効果が出るんです。
例えば、棚にポンと置けるボックス、フタなしで子どもが戻しやすいケース、ラベルを貼りやすいトレーなどは「子どもが自分で片づけられる仕組み」を支えるアイテムとして大活躍。



しかも、子どもの成長や遊びの変化に応じて買い替え・追加しやすいのでコスパも抜群!
私も実際に、家のおもちゃコーナーやクローゼット横に100均グッズを導入してみたところ、「あ、自分で戻してる!」という瞬間が増えてびっくりしました。
どれも100~200円程度で売っていて、「値段=ハードル」にならないのもポイント。



子どもも「ママが買ってくれた!」という安心感&ワクワク感で手に取る率が高めです♪
以下の表は「手に入れやすく、片づけ習慣づくりに使える100均アイテム」の実例です。
お買い物メモとしても使ってくださいね♪
【片づけ習慣づくりに使える100均アイテム】
| 商品名 | 価格(目安) | 販売場所 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|
| マルチケース ライトグレー 20×15.5×9cm | 約110円 | CanDo、ダイソー | 書籍・ぬいぐるみなど少量ジャンルのまとめ収納に。色も淡くインテリアになじむ。 |
| フタがとまるパーツケース | 約110円 | セリア、ダイソー | 部品・小物・アクセサリーなど細かいもの向け。フタ付きで“出しっぱなし”を防げる。 |
| SIKIRI 仕切りケース | 約110円 | セリア | 引き出し内の細分化に便利。子どもにも「どこに入れる?」がわかりやすい。 |
| 収納ケース フタ付 10.7×7.2×3.4cm | 約110円 | ダイソー | 小さなパーツ・アクセ・文具などに。フタ付きで積み重ねも可能。 |
このようなアイテムを「子どもの手が届く」「戻しやすい」「迷わない」収納に配置することで、片づけの習慣化がグッと近づきます。
次に、それぞれの商品を詳しく解説していきます!
① マルチケース ライトグレー


このマルチケースは、100均ながらサイズがしっかりしていて「子どものお気に入りコーナー」や「持ち物少なめジャンル」の収納にぴったりです。



明るいライトグレーがインテリアにもなじみやすく、子ども部屋~リビングの横スペースまで幅広く使えます。
【おすすめポイント】
- 手の届く高さに置けば、子ども自身が“自分のボックス”として管理できる。
- 色が落ち着いているので、おもちゃやグッズを入れても部屋全体が散らかった印象になりづらい。
- サイズが20×15.5×9cmと比較的コンパクトなので、棚中段・低段にも収まりやすい。
- 価格が100〜110円で手軽に買い足し可能。成長や遊び変化に応じて増やせる。
【注意点】
- フタなしタイプ(この商品がそうであれば)だと、ホコリが入りやすいので開けっ放しを避ける工夫を。
- あまりに多くのボックスを並べると、子どもがどれを使うか迷ってしまうため「3個くらいが目安」。
- “自分専用”という認識を持たせるために、ラベルやイラストで自分の名前やイメージをつけておくと効果的。
- 素材・構造が100均クオリティなので、重たい物を入れると底がしなる場合あり。重いおもちゃではなく軽めの物を。
このマルチケースを「お気に入りの本」「ぬいぐるみ」「お出かけセット」などジャンルをざっくり分けて置くだけで、子ども自身が「ここに入れよう」と自然に考えるようになります。



高さをママが届く次の動線に合わせて設定すれば、戻す行動もスムーズに!
② フタがとまるパーツケース


こちらのパーツケースは、細かい物の整理に特化しています。
「ボタン」「レゴ」「アクセサリー」「ひも付きおもちゃ」など、バラバラしがちなモノを「ひとまとめ」にできる優れもの!



フタがしっかり閉まるので散らかる原を防ぎやすいのも魅力です。
【おすすめポイント】
- フタ付きなので子どもが中身をぶちまけにくく、散らかりリスクを抑えられる。
- 透明または半透明タイプなら中身が見えて、子どもも“何が入ってる?”と確認しやすい。
- サイズが小さめなので棚や引き出しの中段・高段にも設置可能。
- 値段が100〜110円なので、複数購入して「細かいジャンルに分ける」ことができる。
【注意点】
- フタの開閉に少し手間がかかるタイプだと、子どもが戻すのを面倒に感じる可能性あり。戻しやすさを優先。
- 小さな仕切りが細か過ぎると、子どもにはどこに入れるか迷いが生じるため“仕切りすぎない”ことが重要。
- 高さや重さを考えて設置場所を選ばないと、子どもが手を伸ばしづらい位置になってしまう。
- 素材が薄めの場合、重い物を入れて長期間使用すると変形・破損の可能性あり。
このパーツケースを、「ブロック用」「マスキングテープ用」「お絵かきキット用」など細かめジャンルで使うと、散らかった引き出しの中がスッキリします。



そして、子どもが「この箱にはこれだね」と把握できていると、戻す行動が考える時間を減らしてくれます。
③ SIKIRI 仕切りケース


どこに何を入れるかがわからないから片づけられないという子どもには、このSIKIRI仕切りケースが救世主。



引き出しや棚の中で、仕切ることで「ここだよ」という明確な分け方を示せるので、迷いを減らせます!
【おすすめポイント】
- 引き出しやケース内で仕切りを立てられるので、収納スペースを無駄なく使える。
- 「絵カード+文字ラベル」で子どもにも何が入るか一目でわかる工夫がしやすい。
- 価格100〜110円と手に取りやすく、複数個使って“引き出し全体を一気に片づけゾーン”に変えられる。
- 親子で「この仕切りは○○」「この仕切りは△△」と会話しながら使えるので、片づけが親子の共同作業になる。
【注意点】
- 仕切り数を増やしすぎると逆に「どこ?」と混乱するので、3〜4区画が目安。
- 引き出しの深さ・幅によっては仕切りが合わずガタつく場合あり。購入前にサイズ確認を。
- 仕切りケース内に物を詰め込みすぎると、子どもが戻す時に“はみ出す”ことがあり、結局散らかる。ゆとりを持たせて。
- 透明仕切りだと背景のごちゃつきが透けて見えるため、ケースや引き出し内の色を統一しておくときれいに見える。
仕切りケースを導入して、例えば「上段:ヘアゴム/中段:ハンドタオル/下段:絵本」というように子どもが自分で「こっち」と判断できるスペースを作ると、戻す習慣が育ちやすくなります。
④ 収納ケース フタ付


このフタ付き小型収納ケースは、「細々アイテムを一つにまとめたい!」という場面にぴったり。



アクセサリー、文房具、おもちゃの小さなパーツなど、子ども部屋でも細かい物の整理に助かります。
【おすすめポイント】
- サイズが小さいので、棚の隅・机の引き出し内・クローゼットの隙間などにフィット。
- フタ付きで積み重ねも可能。子どもにも「箱に入れて重ねる」楽しみが出る。
- 価格が100〜110円なので、複数購入して「アイテム別に分ける」ことが手軽。
- 色展開や透明タイプもあるため“見える化”→子どもが「見えるから戻そう」と思いやすい。
【注意点】
- 小サイズゆえに、子どもが素材を認識しづらい場合「これどこ?」となることも。ラベルや絵を貼ると◎。
- フタを閉める動作も一手間なので、子どもが戻す時のハードルにならない高さ・位置が望ましい。
- 重くて頻繁に出し入れするものには不向き。出し入れ回数・重さを想定して使う。
- 素材によっては透明度・強度が異なるため、高級感を求める方はガラス・木製ケースも検討を。
このケースを「おえかきペンセット」「ヘアピン&ゴム」「チャレンジ教材の付録」などに使ってあげると、子どもは「ここに入れるんだな」と感覚で覚えてくれます。



「箱に入れたらフタ閉めて」までルーティン化できれば、片づけが自動的に流れるようになっていきます。
子どもが片づけたくなる部屋づくり|「声かけ」と「収納アイデア」で変わる習慣まとめ


今回の記事では子どもが片づけたくなる部屋づくりのポイントや、「声かけ」と「収納アイデア」について詳しくご紹介しました!
【子どもが片付けたくなる部屋づくりのポイント】
- 収納を子どもの高さ&動線に合わせる
- 分類はざっくりでOK!
- 「自分のスペース」を作る
「子どもが片づけない」とつい嘆いてしまうけれど、実はやる気がないのではなく、「片づけ方がわからない、面倒に感じる仕組みになっている」だけ、というケースが多いんです。



今回紹介したように、100均グッズを使えば、お金をかけずに「子どもが戻しやすい環境」をつくることができます!
ラベルや色、形で「自分の場所」を認識できるようにしてあげると、自然と片づけが習慣化します。



最初から完璧を目指さず、「ちょっと使ってみよう」くらいの気持ちで十分です。
子どもと一緒にラベルを貼ったり、ボックスを並べたりする過程そのものが「片づけの学び時間」になります。
今回の記事を参考に、お子さんと楽しくお片付けしてみてはいかがでしょうか?
また、片付けについてもっと知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください👇